晴れの国・岡山で30年以上日本語教育に取り組んできた、岡山外語学院。その歴史の中で育まれた地域とのつながりを大切にしながら、世界25の国や地域から訪れた約400名の学生たちに学習環境を提供しています。
約60名の教職員に対しても、キャリアアップのためのサポートや研修などを積極的に行っています。また、幅広い年齢層の教員が在籍しており、子育て世代、介護世代も無理なく柔軟に働ける環境づくりにも取り組んでいるといいます。
そんな同校では、日本語教師としてのキャリアと同時に将来性を重視して教員を採用しているのだとか。「チャレンジしてみたいけど未経験だし…」という方、ぜひご一読ください。
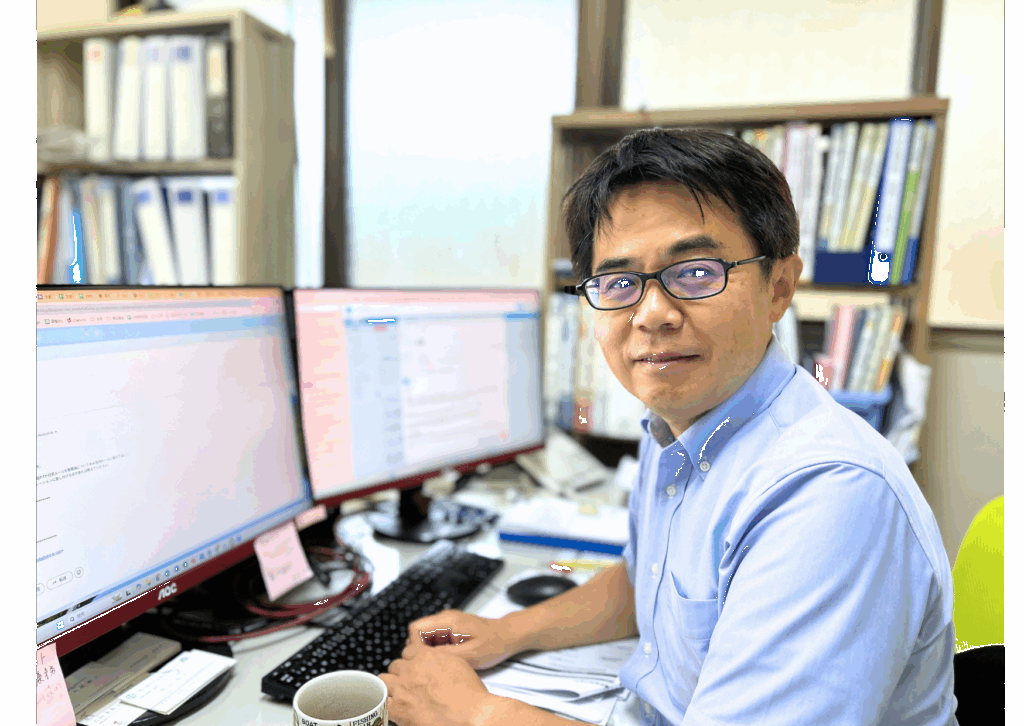
-1024x768.jpg)
(左)尾亦祐司校長
都内で日本語学校の副校長を務めたのち、2024年より本校校長として勤務。
(右)教務主任 中島正恵先生
同校で日本語教師の資格を取得し、2002年より勤務。08年からは日本語教師養成講座の講師も務めています。
最初からできなくても大丈夫。大事なのは姿勢と協調

――まず、岡山外語学院の特色をお聞かせください。
尾亦校長:本校は30年以上前から日本語教育に取り組んできたのですが、昨年には文部科学省登録実践研修機関・登録日本語教員養成機関、本年には認定日本語教育機関として認められました。つまり日本語教育機関としても、登録日本語教員の養成機関としても、文科省より質を担保されているということです。この両方の認定を受けている学校は全国でもまだ少ないと思います。
また9割近くの教員が登録日本語教員の資格を持っているのも特徴の一つです。常勤・非常勤を問わず、教員一人ひとりの希望に合わせて計画的に研修などを受けていただくようにしています。
中島主任:新任の教員に対しても必ず1人のベテラン教員がメンターとして付き、半年ほど伴走する仕組みが整っていますので、未経験の方でも大丈夫です。私も何人か新人の先生を受け持っていますが、授業の作り方などで困ったことがあるといつでも相談に乗っています。
教員だけでなく学生に対しても面倒見のいい学校だと思います。国籍の違う学生一人一人に対して、進路の悩みなど困っていることがあれば教職員みんなで向き合っている雰囲気がありますね。
――教員採用にあたって、大切にされている点について教えてください。
中島主任:採用試験では模擬授業と面接を行いますが、模擬授業ではこちらで決めたお題で45分間授業をしていただきます。よく「私はまだ下手ですから」とおっしゃる方がいますが、私たちはその時点での技術に関してはあまり重視していません。なぜなら研修を受けるうちに上手になっていきますから。それよりも、模擬授業の後の面接でフィードバックを行う際に、私たちの話をきちんと聞いていただけるかどうかが大事かなと思っています。採用されたら多国籍な学生さんへの対応はもちろん、我々とチームで働いてもらいますので、臨機応変に動くことができて、協力していけるような方がいいなと。
未経験の方でも大丈夫です。日本語教員の経験があることよりも、これまでの人生経験を活かしながら学生に向き合ってくれる姿勢があることが大事だと考えています。たとえば子育ての経験があるなら、その経験を活かして結婚・出産をした学生の相談にも乗ることができますよね。人生のあらゆる経験を活かせるのが日本語教師だと思います。
柔軟な働き方に対応。岡山という地域ならではの環境も魅力

――教員の方でも結婚や出産、介護など様々な事情をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。働き方について、気軽に相談できる環境はあるのでしょうか。
中島主任:先ほど申し上げたようにメンター制度がありますが、働き方についてメンターが新任教員から相談を受けることもよくあります。「非常勤の教員から常勤になりたい」とか「家庭の事情で出勤が難しい日があるのですが、どんな形で働けますか」とか、折に触れて色々な相談がありますね。そうした場合は「じゃあ来月はお休みして、再来月また戻って来られますか」というように、柔軟に対応するようにしています。ライフスタイルに合わせて働き方をある程度自分で選べるようにできればと。
他にも、「こういう勉強がしたいんですが、良い研修はありますか?」「この資格受けようと思うんですがまだ早いですか?」というようなキャリア形成についての相談もあります。研修や資格取得については費用援助もありますので、キャリアアップのためにチャレンジしたいことがあるなら積極的に動いてほしいですね。
尾亦校長:キャリア形成について、本校の教員は都会に比べてより地域社会に出ていくような進路を選ぶ方が多いように思います。私は元々東京の日本語学校にいたのですが、そちらでは他の日本語学校に移ったり、別の職種に転職したりするケースが多かったです。しかしこちらでは、転職する場合、地域日本語教育コーディネーターになったり、地域の日本語教室に移ったりする方が多いですね。教員をやりながらボランティア活動も行っている教員もいて、働き方にこだわらず、日本語教育自体に関わることを大切にしている人が多い印象です。

――それは地域との結びつきが大きいということでしょうか。
中島主任:そうですね。東京などの学校と比較すると地域に根差していることは確かかと思います。やはり30年以上の歴史のおかげで、地域の方からの信頼感がありますね。学生も積極的に行事やボランティアに参加してくれます。
地域の清掃や雪かきのボランティアを校内で募集するのですが、希望者が多すぎて人数制限がかかるくらいです。学生の自主性に任せていますが、本当に積極的に参加する学生が多いです。コロナ前には保育園や学童保育に「多様性を子どもたちに学ばせたい」ということで呼ばれたこともあリます。東南アジアではコミュニティの中で子育てする習慣がありますので、そうした地域から来ている学生たちは子どもたちの扱いがとても上手なんですよ。そんな様子を見られるのも我々にとって嬉しいことですね。あとは備前焼の体験に行ったり、和菓子や和食を楽しんだり、日本文化に触れてもらう機会を地域とのつながりの中でたくさんいただいていますね。
――そうした地域との関係性があるからこそ、教員の方々もキャリア形成を考える上で地域に出て働いたりボランティアをしたいと思えたりするのかもしれませんね。
色々な国から来られた学生さんのサポートは大変なことも多いと思いますが、いかがでしょうか。
中島主任:そうですね。多国籍な学生の相談に乗ったり指導をしたりするのはちょっと大変です。約25か国から受け入れを行っていますが、初めて受け入れる国からの学生がいれば、その都度その国の文化について調べるなど、準備をしなければなりません。
日本語学校に限らず教育業界全般に言えることですが、新しいメソッドが次々に出てくるので、その都度勉強して適応することが好きな人でなければこの仕事は難しいのかなと思います。終わりがないことが大変ではありますね。
でも、人が成長していく過程を見るのは楽しいですよ。初めての異国での一人暮らしを通して、学生は語学面だけでなく、人としてぐっと成長します。そこをサポートして見守ることにはとてもやりがいを感じますね。教員にアンケートを取ると、やはり皆そう答えてくれます。
――大変なこともありますが、やりがいは何にも代えられませんね。
では最後に、応募を検討している方にメッセージをお願いします。
尾亦校長:学生400人という中規模校ですが、学校自体も教員も色々なことに挑戦しています。そして、色々な事に挑戦できるオープンな組織風土も持った学校です。チャレンジしたいことがある方はぜひ来てください。
中島主任:私も元々は一般企業に勤めていましたが、本校の養成講座に通って非常勤から始めて、今では教務主任として頑張っています。経験がある方も未経験の方も、授業がうまくいかなくても大丈夫です。それだけ伸びしろがあると考えてください。今の技術ではなく、将来性や素質を見て採用していますので、ぜひ応募してみてください。
――ありがとうございました。


