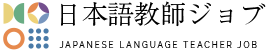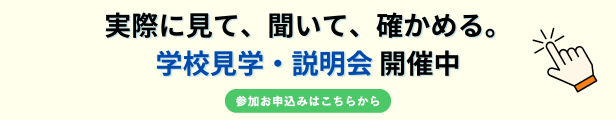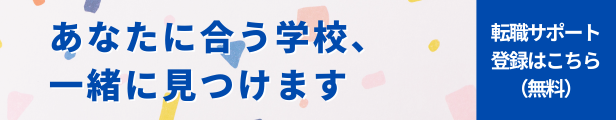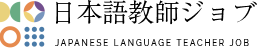技能実習制度が「育成就労制度」に―日本語教師が知っておくべきポイント
2024年、日本政府はこれまでの技能実習制度を廃止し、新たに「育成就労制度」を導入することを決定しました。この制度改正の目的は、日本の特定産業分野での人材確保を図るとともに、実習生の労働環境とキャリアパスを改善することにあります。従来の技能実習制度は「技術移転」を目的としていましたが、新制度ではより明確に「特定技能への移行」を前提とし、在留資格や転職の柔軟性が見直されています。
この変化に伴い、実習生の日本語学習の要件も強化され、企業や教育機関に求められる役割が大きく変わります。特に日本語教師にとっては、新しい制度の下でどのような指導が求められるのかを理解することが重要です。本記事では、日本語教師が知っておくべきポイントを解説します。
この変化に伴い、実習生の日本語学習の要件も強化され、企業や教育機関に求められる役割が大きく変わります。特に日本語教師にとっては、新しい制度の下でどのような指導が求められるのかを理解することが重要です。本記事では、日本語教師が知っておくべきポイントを解説します。
1. 日本語教育の要件変更
育成就労制度では、実習生の日本語能力向上がこれまで以上に重視されています。具体的には、
・入国前後で日本語能力試験N5程度の基礎力を習得することが必須
・1年目終了時にN5相当、3年目終了時にはN4合格が標準的なゴール
この基準は、特定技能1号へ移行するための要件(多くの分野でN4以上が必要)に対応するものです。そのため、日本語教師には、試験対策だけでなく、実習生が日常生活や業務で実践的に活用できる日本語スキルを教えることが求められます。
・入国前後で日本語能力試験N5程度の基礎力を習得することが必須
・1年目終了時にN5相当、3年目終了時にはN4合格が標準的なゴール
この基準は、特定技能1号へ移行するための要件(多くの分野でN4以上が必要)に対応するものです。そのため、日本語教師には、試験対策だけでなく、実習生が日常生活や業務で実践的に活用できる日本語スキルを教えることが求められます。
2. 日本語能力の評価基準の変化
これまでは、日本語能力の評価は主に面接や簡単な試験に依存していました。しかし、新制度では、JLPT(日本語能力試験)やJFT-Basic(特定技能評価試験)などの客観的な試験結果が求められます。
・試験合格が在留継続の要件になるため、日本語教師は実習生が確実に試験に合格できるよう指導する必要があります。
・評価時期も明確化されており、1年目終了時と3年目終了時に一定の達成度を測ることが求められます。
そのため、日本語教師には、試験対策に特化した指導と、実務に即した日本語会話のトレーニングの両方が必要になります。
・試験合格が在留継続の要件になるため、日本語教師は実習生が確実に試験に合格できるよう指導する必要があります。
・評価時期も明確化されており、1年目終了時と3年目終了時に一定の達成度を測ることが求められます。
そのため、日本語教師には、試験対策に特化した指導と、実務に即した日本語会話のトレーニングの両方が必要になります。
3. 企業に対する日本語教育支援の義務
育成就労制度では、企業に対しても日本語教育支援の義務が課されるようになります。これにより、受け入れ企業は、
・日本語学習環境の整備(社内クラス、オンライン教材提供など)
・日本語教師の確保、または外部教育機関との連携
・業務中の日本語サポートの充実
といった取り組みを強化する必要があります。
日本語教師は、企業と連携して、
・勤務スケジュールに配慮した学習計画の提案
・学習成果の可視化とフィードバックの提供
・職場での実践的な日本語使用を促進する教材開発
などを行い、実習生の言語習得を支援する役割を果たすことになります。
・日本語学習環境の整備(社内クラス、オンライン教材提供など)
・日本語教師の確保、または外部教育機関との連携
・業務中の日本語サポートの充実
といった取り組みを強化する必要があります。
日本語教師は、企業と連携して、
・勤務スケジュールに配慮した学習計画の提案
・学習成果の可視化とフィードバックの提供
・職場での実践的な日本語使用を促進する教材開発
などを行い、実習生の言語習得を支援する役割を果たすことになります。
4. 実習生の日本語学習支援の必要性
働きながら日本語を習得するのは簡単ではありません。特に、新制度ではN4レベルの取得が求められるため、モチベーション管理や継続的なサポートが不可欠です。
・職場で使う日本語(業務指示、報告、トラブル対応)を優先的に指導
・生活に直結する日本語(病院、銀行、市役所での会話)を強化
・オンライン教材やアプリの活用で、学習機会を増やす
また、自治体や地域の日本語支援団体と連携し、
・ボランティア日本語教室の活用
・企業向けの補助金を利用した学習支援
などを検討することも、教師にとって重要な役割となるでしょう。
・職場で使う日本語(業務指示、報告、トラブル対応)を優先的に指導
・生活に直結する日本語(病院、銀行、市役所での会話)を強化
・オンライン教材やアプリの活用で、学習機会を増やす
また、自治体や地域の日本語支援団体と連携し、
・ボランティア日本語教室の活用
・企業向けの補助金を利用した学習支援
などを検討することも、教師にとって重要な役割となるでしょう。
まとめ
技能実習制度から育成就労制度への移行により、日本語教育の重要性がこれまで以上に高まります。特に、在留資格の継続や特定技能への移行に直結する日本語能力試験の合格が必須となるため、日本語教師の役割はますます重要になります。
・試験対策と実務日本語のバランスを考えた指導
・企業との連携による学習環境の整備
・実習生のモチベーション維持と継続的なサポート
これらを意識することで、育成就労制度のもとでより良い日本語教育を提供し、実習生のキャリア発展に貢献することができます。
今後、企業や監理団体と協力しながら、日本語教師としてどのように関与できるかを考えていくことが重要になるでしょう。
・試験対策と実務日本語のバランスを考えた指導
・企業との連携による学習環境の整備
・実習生のモチベーション維持と継続的なサポート
これらを意識することで、育成就労制度のもとでより良い日本語教育を提供し、実習生のキャリア発展に貢献することができます。
今後、企業や監理団体と協力しながら、日本語教師としてどのように関与できるかを考えていくことが重要になるでしょう。
求人増加中!日本国内の日本語学校の新着求人は↓
新着の記事
- 【新宿】GENKI JACS 東京校 採用説明会
- 第16回埼玉地区日本語教育機関合同採用説明会開催のお知らせ
- 【大久保】エリートビジョン日本語学校採用説明会
- 【愛知県岡崎市】ウイン日本語学院採用説明会
- 【オンライン日本語学校】Akira Online Japanese School TOKYO 採用説明会
- 【日暮里・大塚・高田馬場】京進ランゲージアカデミー採用説明会
- 【香港】Central Japanese Club 採用説明会
- 自民・維新連立がもたらす変化とは―日本語教育と外国人政策のこれからを読み解く―
- 国家資格ができても、日本語教師の給料は上がらない本当の理由
- 【令和8年度文科省予算】日本語教育に何が起きる?教師のキャリアと求人動向を解説|日本語教師ジョブ