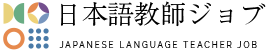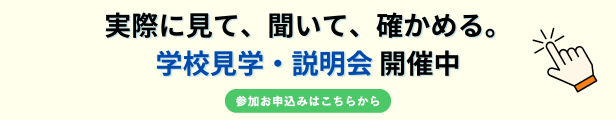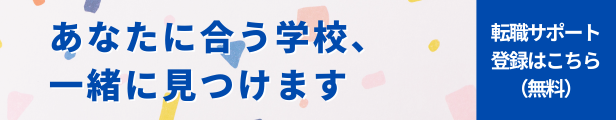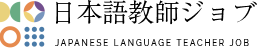外国ルーツの子どもたちが「隔離」される現実 - 特別支援学級の歪んだ実態
| 教室で起きている「静かな排除」
「また一人、特別支援学級に送られた...」
関東の公立小学校で働く教員のつぶやきが、今の日本の教育現場の深刻な問題を物語っています。母語が日本語ではない子どもたちが、発達障害と誤診され、特別支援学級に振り分けられる——そんな事態が全国で頻発しているのです。
担任教師が授業中に気づく光景は、いつも同じパターンです。「言葉が通じない」「指示が入らない」「友達とやりとりができない」。しかし、その背景にあるのは発達障害の特性なのか、それとも単なる日本語の未習得なのか——その判断は極めて困難です。
結果として、教室で浮いてしまう子どもを見た担任は悩み抜いた末、「この子にとってベストな環境」を求めて特別支援学級への移籍を決断します。果たしてこれは適切な支援なのか、それとも事実上の排除なのでしょうか。
関東の公立小学校で働く教員のつぶやきが、今の日本の教育現場の深刻な問題を物語っています。母語が日本語ではない子どもたちが、発達障害と誤診され、特別支援学級に振り分けられる——そんな事態が全国で頻発しているのです。
担任教師が授業中に気づく光景は、いつも同じパターンです。「言葉が通じない」「指示が入らない」「友達とやりとりができない」。しかし、その背景にあるのは発達障害の特性なのか、それとも単なる日本語の未習得なのか——その判断は極めて困難です。
結果として、教室で浮いてしまう子どもを見た担任は悩み抜いた末、「この子にとってベストな環境」を求めて特別支援学級への移籍を決断します。果たしてこれは適切な支援なのか、それとも事実上の排除なのでしょうか。
| 数字が示す衝撃の現実
文部科学省の2016年調査が明らかにした数字は、この問題の深刻さを如実に示しています。
外国籍の子どもの特別支援学級在籍率:5.2%
日本人全体の平均:2.3%
約2倍以上の開きがある数字です。さらに驚くべきことに、浜松市では外国籍児童の5人に1人が支援学級に通っていた年もあり、岡山県総社市では19.3%という異常な数値を記録しました。
これらの数字が示しているのは、明らかに「過剰な振り分け」の傾向です。統計学的に考えても、外国籍の子どもだけが発達障害の発症率が高いなどということはありえません。
外国籍の子どもの特別支援学級在籍率:5.2%
日本人全体の平均:2.3%
約2倍以上の開きがある数字です。さらに驚くべきことに、浜松市では外国籍児童の5人に1人が支援学級に通っていた年もあり、岡山県総社市では19.3%という異常な数値を記録しました。
これらの数字が示しているのは、明らかに「過剰な振り分け」の傾向です。統計学的に考えても、外国籍の子どもだけが発達障害の発症率が高いなどということはありえません。
| 「言葉の壁」が生む誤診の連鎖
この異常な状況の根本原因は、「言葉の壁」にあります。
知能検査や発達評価は日本語で行われるのが一般的で、日本語に不自由がある子どもは必然的に「低いスコア」が出がちです。教師や医師がその結果をもとに支援が必要と判断し、支援学級へ送る——このプロセスで「本当は定型発達なのに」と後から判明するケースが珍しくありません。
つまり、言語能力の問題が発達障害として誤診され、子どもたちが不適切な環境に置かれているのです。
知能検査や発達評価は日本語で行われるのが一般的で、日本語に不自由がある子どもは必然的に「低いスコア」が出がちです。教師や医師がその結果をもとに支援が必要と判断し、支援学級へ送る——このプロセスで「本当は定型発達なのに」と後から判明するケースが珍しくありません。
つまり、言語能力の問題が発達障害として誤診され、子どもたちが不適切な環境に置かれているのです。
| 制度の穴が生む「見えない子どもたち」
問題をさらに複雑にしているのは、日本の学校制度そのものの構造的な問題です。
外国籍の子どもには「就学義務」が課されていません。教育委員会から就学案内はされるものの、最終的に学校に通うかどうかは家庭の判断に委ねられています。この制度の穴により、「就学不明児童」が生まれ、支援の網から漏れ落ちる子どもたちが存在します。
さらに深刻なのは、専門的な通訳やバイリンガル支援員の圧倒的な不足です。保護者面談や診断の場に通訳がいないことで、十分な合意形成がなされないまま、子どもが支援学級に送られてしまいます。
制度は「本人と保護者の意思を尊重する」と定めているにも関わらず、現実にはそれが機能していないのです。
外国籍の子どもには「就学義務」が課されていません。教育委員会から就学案内はされるものの、最終的に学校に通うかどうかは家庭の判断に委ねられています。この制度の穴により、「就学不明児童」が生まれ、支援の網から漏れ落ちる子どもたちが存在します。
さらに深刻なのは、専門的な通訳やバイリンガル支援員の圧倒的な不足です。保護者面談や診断の場に通訳がいないことで、十分な合意形成がなされないまま、子どもが支援学級に送られてしまいます。
制度は「本人と保護者の意思を尊重する」と定めているにも関わらず、現実にはそれが機能していないのです。
| 教師たちの板挟み状態
現場の教師たちは、深刻なジレンマに直面しています。
通常学級の教師は「この子を支えたい」という想いと、「時間もスキルも足りない」という現実の板挟みにあっています。授業中、他の30人を見ながら、母語が違う1人に個別支援をするのは物理的に不可能です。特別支援学級に送るという選択肢は、本人のためというより「仕方がない」という側面が強いのが実情です。
一方、特別支援学級の教師は別の苦悩を抱えています。「発達障害の専門家として雇われたのに、実際は日本語教師になっている」という声が現場から上がっています。
多くの教員が指摘するのは、「日本語指導と発達障害支援の専門性は全く違う。それが現場ではごちゃ混ぜになっている」という現実です。
通常学級の教師は「この子を支えたい」という想いと、「時間もスキルも足りない」という現実の板挟みにあっています。授業中、他の30人を見ながら、母語が違う1人に個別支援をするのは物理的に不可能です。特別支援学級に送るという選択肢は、本人のためというより「仕方がない」という側面が強いのが実情です。
一方、特別支援学級の教師は別の苦悩を抱えています。「発達障害の専門家として雇われたのに、実際は日本語教師になっている」という声が現場から上がっています。
多くの教員が指摘するのは、「日本語指導と発達障害支援の専門性は全く違う。それが現場ではごちゃ混ぜになっている」という現実です。
| 「収容所」と呼ばれる特別支援学級
ブラジル人の保護者から「支援学級は外国人のための収容所みたい」との声が上がったことがあります。差別的な扱いを受けているという被害意識、学校に対する不信、そして「通わせたくない」という親の心理が生まれています。
この悪循環が進むとどうなるでしょうか。登校拒否、学力低下、就労困難、貧困、そして社会からの孤立。社会参加の機会を奪われるだけでなく、最終的には社会不安の要因にもなりかねません。
この悪循環が進むとどうなるでしょうか。登校拒否、学力低下、就労困難、貧困、そして社会からの孤立。社会参加の機会を奪われるだけでなく、最終的には社会不安の要因にもなりかねません。
| 希望を示す先進自治体の取り組み
こうした暗い現実の中で、希望を示す自治体の取り組みも存在します。
横浜市では「外国籍の子どもが5人以上いる小学校には必ず日本語支援教室を置く」制度を整備。
名古屋市では発達障害を分かりやすく解説した多言語パンフレットを配布。
大阪市では就学前に日本語や学校生活を学べるプレスクールを実施。
これらの取り組みは、支援学級に安易に送らないための「前さばき」として注目されています。
横浜市では「外国籍の子どもが5人以上いる小学校には必ず日本語支援教室を置く」制度を整備。
名古屋市では発達障害を分かりやすく解説した多言語パンフレットを配布。
大阪市では就学前に日本語や学校生活を学べるプレスクールを実施。
これらの取り組みは、支援学級に安易に送らないための「前さばき」として注目されています。
| 今こそ必要な制度改革
この問題は単なる教育課題ではありません。多文化共生の実現、社会的不平等の是正、日本社会の持続可能性に直結する「社会課題」なのです。
すべての子どもに、適切な教育と支援を。母語が違っても、特性があっても、「排除ではなく、包摂」を。
特別支援学級は本来、特性に応じた支援の場であるべきです。その理念が、国籍や言語によって歪められることがあってはなりません。
全国的な制度見直しと支援強化が、今、急務です。
外国ルーツの子どもたちが「隔離」される現実を変えるために、私たち一人ひとりが声を上げ、行動を起こすときが来ています。
すべての子どもに、適切な教育と支援を。母語が違っても、特性があっても、「排除ではなく、包摂」を。
特別支援学級は本来、特性に応じた支援の場であるべきです。その理念が、国籍や言語によって歪められることがあってはなりません。
全国的な制度見直しと支援強化が、今、急務です。
外国ルーツの子どもたちが「隔離」される現実を変えるために、私たち一人ひとりが声を上げ、行動を起こすときが来ています。
求人増加中!日本国内の日本語学校の新着求人は↓