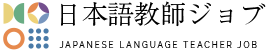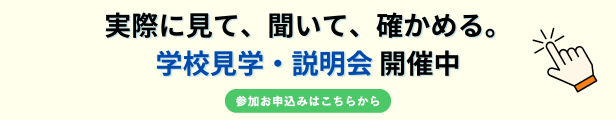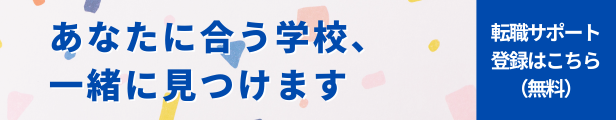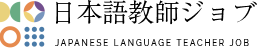自民・維新連立がもたらす変化とは―日本語教育と外国人政策のこれからを読み解く―
1. 「共生」から「管理」へ──政策の軸足が変わる兆し
2025年10月、自民党と日本維新の会が「連立政権合意書」を締結しました。
その中の第九章「人口政策及び外国人政策」には、こんな一文があります。
「外国人比率が高くなった場合の社会との摩擦の観点から、外国人の受け入れに関する数値目標や基本方針を明記した『人口戦略』を策定する」
これまでの日本の外国人政策は、公明党が主導してきた「共生と支援」を軸にしてきました。ところが、維新が政権に加わったことで「秩序と効率」を重視する方向へとバランスが変わりつつあります。つまり、「受け入れを増やす」から「どれくらい、どんな人を受け入れるかを管理する」時代に入ったということです。日本語学校にとっても、「支援の現場」から「社会統合の最前線」へと役割が少しずつ変化していく可能性があります。
その中の第九章「人口政策及び外国人政策」には、こんな一文があります。
「外国人比率が高くなった場合の社会との摩擦の観点から、外国人の受け入れに関する数値目標や基本方針を明記した『人口戦略』を策定する」
これまでの日本の外国人政策は、公明党が主導してきた「共生と支援」を軸にしてきました。ところが、維新が政権に加わったことで「秩序と効率」を重視する方向へとバランスが変わりつつあります。つまり、「受け入れを増やす」から「どれくらい、どんな人を受け入れるかを管理する」時代に入ったということです。日本語学校にとっても、「支援の現場」から「社会統合の最前線」へと役割が少しずつ変化していく可能性があります。
2. 外国資本と教育分野──まだ静かだが、確実に進む変化
今回の合意書では、「外国人および外国資本による土地取得規制を強化する法案を策定する」と明記されています。対象は主に防衛施設やインフラ周辺ですが、背景には「外国資本の日本進出が多様化している」という現実があります。実際、日本語学校業界でもここ数年、東南アジアや中華圏の企業、教育関連ファンドなどが静かに参入を進めています。買収・設立ともに数はまだ多くありませんが、確実に増えているのは事実です。
現時点では、文化庁や出入国在留管理庁の審査で「資金の出所」や「実質的支配者」まで詳細に問われることはありません。しかし、外資参入の拡大とともに、教育機関の設置主体や資金の透明性をめぐる具体的な規制が今後検討される可能性があります。
安全保障政策の延長線上で、教育分野にも透明性確保の仕組みが導入される――そんな将来像を、政府内ではすでに見据え始めているのかもしれません。
現時点では、文化庁や出入国在留管理庁の審査で「資金の出所」や「実質的支配者」まで詳細に問われることはありません。しかし、外資参入の拡大とともに、教育機関の設置主体や資金の透明性をめぐる具体的な規制が今後検討される可能性があります。
安全保障政策の延長線上で、教育分野にも透明性確保の仕組みが導入される――そんな将来像を、政府内ではすでに見据え始めているのかもしれません。
3. 人口減少と外国人受け入れ──「別々の話」ではなくなる
合意書では、「政府に人口減少対策本部(仮称)を設置し、子育て政策と外国人政策を包括的に進める」との方針も掲げられています。
これまで「少子化対策」と「外国人受け入れ」は別枠で語られてきましたが、今後は「人口戦略」という同じ土俵で扱われることになります。その意味するところは明確です。外国人が「人口減少社会を支える労働力」として位置づけられ、日本語教育が“就労のための教育”として再定義されていくということです。
これまで「文化理解」「地域共生」を重視してきた教育現場も、今後は「働くための日本語教育」「目的別の実践教育」への転換が求められるかもしれません。
これまで「少子化対策」と「外国人受け入れ」は別枠で語られてきましたが、今後は「人口戦略」という同じ土俵で扱われることになります。その意味するところは明確です。外国人が「人口減少社会を支える労働力」として位置づけられ、日本語教育が“就労のための教育”として再定義されていくということです。
これまで「文化理解」「地域共生」を重視してきた教育現場も、今後は「働くための日本語教育」「目的別の実践教育」への転換が求められるかもしれません。
4. 「教育の適正化」という名の再編が進む可能性
教育分野の章には次のような一文があります。
人口減少に伴い、大学数および規模の適正化を図る。
留学生の多くが進学を希望する大学・専門学校の統廃合が進めば「留学生の進学先が減る」=「日本語学校での進学支援や募集活動にも影響する」という構図が生まれます。特に、地方の私立大学や短期大学が統合・縮小される場合、地方都市の日本語学校では「進学先の選択肢減少」により、学生募集や在籍数に間接的な影響が及ぶ可能性があります。
つまり、大学再編の動きは「上流の話」に見えて、実際には日本語学校の運営や留学生のキャリア設計にも静かに波紋を広げていく政策なのだと思います。
人口減少に伴い、大学数および規模の適正化を図る。
留学生の多くが進学を希望する大学・専門学校の統廃合が進めば「留学生の進学先が減る」=「日本語学校での進学支援や募集活動にも影響する」という構図が生まれます。特に、地方の私立大学や短期大学が統合・縮小される場合、地方都市の日本語学校では「進学先の選択肢減少」により、学生募集や在籍数に間接的な影響が及ぶ可能性があります。
つまり、大学再編の動きは「上流の話」に見えて、実際には日本語学校の運営や留学生のキャリア設計にも静かに波紋を広げていく政策なのだと思います。
5. 変わるのは制度、変わらないのは教育の使命
今回の自民・維新連立は、外国人政策と日本語教育政策の「地殻変動」を意味します。外国人の受け入れを「数」でなく「質」で管理する方向に舵を切る中で、日本語学校や教師には、「社会に信頼される教育」の実践がこれまで以上に求められます。一方で、これはチャンスでもあります。透明性を高め、教育の質を磨き、地域や社会に開かれた学校をつくることが、これからの競争力そのものになるのです。
政治の風向きは変わっても、教育の使命は変わりません。むしろ、「日本語教育」が国の未来戦略の中でどんな役割を果たすのか――その問いに答える時代が、いま始まっています。
政治の風向きは変わっても、教育の使命は変わりません。むしろ、「日本語教育」が国の未来戦略の中でどんな役割を果たすのか――その問いに答える時代が、いま始まっています。