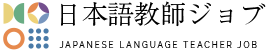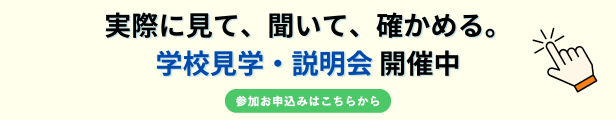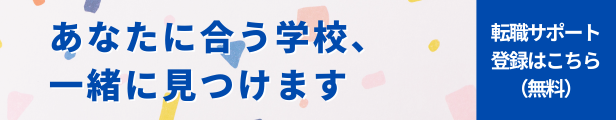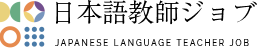【日本語学校必読】「認定日本語教育機関活用促進事業」第1回 採択団体リストと特徴
はじめに
文部科学省では、日本語教育機関を核に産業界等からの教育投資を呼び込み、日本語教育の質向上につなげる「好循環モデル」の構築・普及を目指す事業(認定日本語教育機関活用促進事業)を開始しました
。
本事業の初年度・第1回公募(第1次公募)においては、全国から公募した提案の中から「好循環モデル構築実施団体」として複数の団体が採択されました。
本記事では、初年度第1回で採択された団体(採択事業)の特徴を、公開情報に基づき総合的に分析します。
。
本事業の初年度・第1回公募(第1次公募)においては、全国から公募した提案の中から「好循環モデル構築実施団体」として複数の団体が採択されました。
本記事では、初年度第1回で採択された団体(採択事業)の特徴を、公開情報に基づき総合的に分析します。
採択団体の種類・組織形態
初回公募で採択された団体の主たる実施主体は、日本語学校等の教育機関や関連法人が中心となっています。例えば、学校法人(専門学校や日本語学校の運営母体)に属する機関が多数を占めており、東川国際文化福祉専門学校(学校法人北工学園)や専門学校アリス学園(学校法人アリス国際学園)などが代表です。
また、民間の企業も複数採択されており、Ibis株式会社(人材紹介・特定技能支援の企業)や株式会社アイ・シー・エイ(日本語学校グループICAの運営企業)、株式会社TCJグローバル(東京中央日本語学院)などが名を連ねています。
さらに、非営利団体/NPO等としては公益財団法人名古屋YWCA(国際NGO系の教育団体)、一般社団法人国際パートナーシップセンター、一般社団法人全日本教育研究会といった法人が採択されています。大規模な公益法人では一般財団法人日本国際協力センター(JICE)も採択され、宿泊業等の業界団体との連携事業を担います。一方で、自治体や大学が主申請者となった事例は初回には見られませんでした(ただし後述のように自治体・大学はパートナーとして連携参加)。
総じて、採択団体は日本語教育に関わる民間・非営利の主体が中心であり、多様な組織形態(学校法人、公益法人、一般社団法人、株式会社等)が含まれていることが特徴です。
また、民間の企業も複数採択されており、Ibis株式会社(人材紹介・特定技能支援の企業)や株式会社アイ・シー・エイ(日本語学校グループICAの運営企業)、株式会社TCJグローバル(東京中央日本語学院)などが名を連ねています。
さらに、非営利団体/NPO等としては公益財団法人名古屋YWCA(国際NGO系の教育団体)、一般社団法人国際パートナーシップセンター、一般社団法人全日本教育研究会といった法人が採択されています。大規模な公益法人では一般財団法人日本国際協力センター(JICE)も採択され、宿泊業等の業界団体との連携事業を担います。一方で、自治体や大学が主申請者となった事例は初回には見られませんでした(ただし後述のように自治体・大学はパートナーとして連携参加)。
総じて、採択団体は日本語教育に関わる民間・非営利の主体が中心であり、多様な組織形態(学校法人、公益法人、一般社団法人、株式会社等)が含まれていることが特徴です。
地理的分布と地域的特徴
採択された事業実施団体の所在地・活動地域は日本全国にわたり分散しています。北は北海道から南は九州までカバーされており、たとえば北海道東川町の専門学校(東川国際文化福祉専門学校)が地方創生の一環で外国人介護人材の育成支援モデルを展開しています。中部地方では愛知県名古屋市に拠点を置く名古屋YWCAによる事業(外国ルーツの高校生・留学生支援)が採択されているほか、愛知県岡崎市の日本語学校(YAMASA言語文化学院)や名古屋近郊の日本語学校複数が参画する事例もあります。
首都圏では東京に本校を持つメロス言語学院(学校法人香川学園)や千駄ヶ谷外語学院(学校法人千駄ヶ谷教育学園)など複数の日本語学校が採択団体となっており、埼玉県の与野学院日本語学校の事例も含まれます。中国地方では岡山県(岡山外語学院)の取り組み、九州では佐賀県嬉野市の温泉旅館を活用した日本語学校開設モデルが見られます。
このように都市部と地方の双方から幅広く選ばれており、それぞれの地域ニーズに応じた特色あるモデルが立ち上がっています。大都市圏では主に留学生の就職支援や企業内研修モデルが多く、地方では観光・介護など地域産業への定着支援や基盤整備型のモデルが目立ちます。全体として、日本全国に好循環モデルの実践例が点在しており、特に外国人材受入れが進む地域(首都圏・中京圏など)と、人手不足や地域活性化ニーズが高い地方圏の双方がバランスよく含まれている点が特徴と言えます。
首都圏では東京に本校を持つメロス言語学院(学校法人香川学園)や千駄ヶ谷外語学院(学校法人千駄ヶ谷教育学園)など複数の日本語学校が採択団体となっており、埼玉県の与野学院日本語学校の事例も含まれます。中国地方では岡山県(岡山外語学院)の取り組み、九州では佐賀県嬉野市の温泉旅館を活用した日本語学校開設モデルが見られます。
このように都市部と地方の双方から幅広く選ばれており、それぞれの地域ニーズに応じた特色あるモデルが立ち上がっています。大都市圏では主に留学生の就職支援や企業内研修モデルが多く、地方では観光・介護など地域産業への定着支援や基盤整備型のモデルが目立ちます。全体として、日本全国に好循環モデルの実践例が点在しており、特に外国人材受入れが進む地域(首都圏・中京圏など)と、人手不足や地域活性化ニーズが高い地方圏の双方がバランスよく含まれている点が特徴と言えます。
支援対象となる外国人の属性
各採択事業が支援・対象としている外国人の属性は多岐にわたっており、在留資格や年齢層、出身国も様々です。
まず、労働分野では介護分野の外国人労働者を対象とするモデルがあります。例えば北海道の事例では、外国人介護人材(介護福祉士候補など)の地域定着支援が掲げられています。宿泊業(ホテル・旅館)や自動車運送業(トラック運送)といった特定産業分野で働く外国人向けには、業界ニーズに即した日本語教育カリキュラム開発が行われます。これらは技能実習や特定技能といった在留資格で来日している外国人労働者を主な対象としていると考えられます。
また、日本語を学ぶ留学生も重要な対象です。名古屋YWCAの事業では「外国にルーツを持つ高校生」および留学生のキャリア形成支援を掲げており、高校年代(10代後半)の留学生・移民ルーツの生徒まで含めた支援を特徴とします。東京の日本語学校による複数の事業(千駄ヶ谷外語学院やTCJグローバル等)でも、日本の企業への就職を希望する外国人留学生を主な対象として、ビジネス日本語研修や就職マッチング支援を実施しています。
一方、生活者として地域に定住する外国人への支援も見逃せません。埼玉の与野学院日本語学校の取組では、日本で生活する外国人住民向けに、日本語能力がごく初歩段階(CEFRで言うプレA1レベル)の人々に対するカリキュラム開発を行っています。これは家族帯同や定住者など、日本語初学者として地域社会で暮らす外国人住民を念頭に置いたものです。
さらに、高度人材を対象とするモデルも含まれています。石川県の専門学校アリス学園が代表を務める事例では、インド人エンジニアを地元企業が受け入れる際の就労前後にわたる日本語教育支援が計画されており、エンジニア等の専門人材(技術・人文知識・国際業務などの在留資格者)へのサポートとなっています。また、佐賀県嬉野市の温泉旅館内に新設された日本語学校では、アジアの5か国(インド、ウズベキスタン等)から集まった平均年齢25.9歳の留学生41名が学んでおり、地域で働き定住することを目指しています。
このように、対象となる外国人の属性は学生から社会人まで幅広く、在留資格も「留学」「特定技能」「技能実習」「定住者」「技術・人文知識・国際業務」等、多岐に及ぶことがうかがえます。出身国・地域についてはアジア諸国が中心と推察されますが、事例によって特定の国籍層にフォーカスするもの(例:インド人、中国系高校生等)から、多国籍な受入れを行うもの(例:嬉野の事例ではインド・ウズベキスタン含む5か国)まで様々です。総じて各モデルは、地域の産業ニーズや社会課題に対応する形で、対象とする外国人の層を明確に定めた上で日本語教育支援を提供している点が特徴といえます。
まず、労働分野では介護分野の外国人労働者を対象とするモデルがあります。例えば北海道の事例では、外国人介護人材(介護福祉士候補など)の地域定着支援が掲げられています。宿泊業(ホテル・旅館)や自動車運送業(トラック運送)といった特定産業分野で働く外国人向けには、業界ニーズに即した日本語教育カリキュラム開発が行われます。これらは技能実習や特定技能といった在留資格で来日している外国人労働者を主な対象としていると考えられます。
また、日本語を学ぶ留学生も重要な対象です。名古屋YWCAの事業では「外国にルーツを持つ高校生」および留学生のキャリア形成支援を掲げており、高校年代(10代後半)の留学生・移民ルーツの生徒まで含めた支援を特徴とします。東京の日本語学校による複数の事業(千駄ヶ谷外語学院やTCJグローバル等)でも、日本の企業への就職を希望する外国人留学生を主な対象として、ビジネス日本語研修や就職マッチング支援を実施しています。
一方、生活者として地域に定住する外国人への支援も見逃せません。埼玉の与野学院日本語学校の取組では、日本で生活する外国人住民向けに、日本語能力がごく初歩段階(CEFRで言うプレA1レベル)の人々に対するカリキュラム開発を行っています。これは家族帯同や定住者など、日本語初学者として地域社会で暮らす外国人住民を念頭に置いたものです。
さらに、高度人材を対象とするモデルも含まれています。石川県の専門学校アリス学園が代表を務める事例では、インド人エンジニアを地元企業が受け入れる際の就労前後にわたる日本語教育支援が計画されており、エンジニア等の専門人材(技術・人文知識・国際業務などの在留資格者)へのサポートとなっています。また、佐賀県嬉野市の温泉旅館内に新設された日本語学校では、アジアの5か国(インド、ウズベキスタン等)から集まった平均年齢25.9歳の留学生41名が学んでおり、地域で働き定住することを目指しています。
このように、対象となる外国人の属性は学生から社会人まで幅広く、在留資格も「留学」「特定技能」「技能実習」「定住者」「技術・人文知識・国際業務」等、多岐に及ぶことがうかがえます。出身国・地域についてはアジア諸国が中心と推察されますが、事例によって特定の国籍層にフォーカスするもの(例:インド人、中国系高校生等)から、多国籍な受入れを行うもの(例:嬉野の事例ではインド・ウズベキスタン含む5か国)まで様々です。総じて各モデルは、地域の産業ニーズや社会課題に対応する形で、対象とする外国人の層を明確に定めた上で日本語教育支援を提供している点が特徴といえます。
実施内容の特徴(日本語教育の手法・ICT活用・地域連携 等)
各採択事業は、それぞれ工夫を凝らした日本語教育の提供手法やプログラム内容を特徴としています。共通する狙いは「質の高い日本語教育をニーズに応じて提供すること」ですが、そのアプローチは多彩です。
まず、ICTの活用が目立ちます。例えば、千駄ヶ谷外語学院の事例では「ビジネス日本語eラーニング教材と企業交流イベントを組み合わせた」就職支援を行うとされ、オンライン学習教材を積極的に取り入れています。また、全日本教育研究会・ミッドリーム日本語学校の事例では「AIを活用したビルメンテナンス業界向けの発話型学習教材の開発」に取り組む計画であり、人工知能を用いた対話練習教材という先進的手法が特徴です。さらに、岡山外語学院のプロジェクトでは、新たに創設される育成就労制度(技能実習制度に代わる新制度)を見据えて「オンライン日本語講習カリキュラムの開発」を行うとされ、遠隔で受講できる講習コンテンツの整備を進めています。このようにデジタル技術を取り入れることで、忙しい就労者でも学びやすくしたり、広域の学習者に対応したりする工夫が見られます。
次に、実践的・現場密着型の教育も多くの事業で重視されています。佐賀県嬉野市のモデルケースでは、旅館という現場で外国人留学生がアルバイト勤務をしながら日本語を学ぶ仕組みを構築し、教室の学びと職場経験を一体化させています。このようなインターンシップ組み込み型の教育プログラムによって、日本語学習が机上のものに留まらず、実際の業務・地域生活と結びつくように設計されています。同様に、石川のアリス学園による事業でもインド人技術者に対し就労前研修と就労後フォローアップを一貫して行うモデルを掲げており、職場定着を見据えた長期的な日本語教育支援が特徴です。また、TCJグローバルの事例では、外国人人材の企業紹介(就職あっせん)と日本語教育を一体化したサービス提供モデルを構築するとされています。これは人材紹介会社の機能と語学研修を組み合わせることで、「採用前の日本語研修→就労→就労後の継続研修」という切れ目ない支援を実現しようとするものです。
さらに、新しいカリキュラムや教材の開発も多くの事業でキーワードとなっています。JICEが中心となる事業では、宿泊・運送業界ごとに異なるニーズに対応する業種別日本語教育モデルカリキュラムの開発が掲げられています。これは業界団体と協力し、専門用語や接客表現など各業種に適した教材・カリキュラムを整える試みです。同様に、埼玉の与野学院日本語学校の事例ではプレA1レベル(超入門レベル)のカリキュラム開発がうたわれており、読み書きもままならない初心者向け教材の整備を進めています。これらの新カリキュラム策定は、他地域への汎用も視野に入れたモデルづくりと言え、完成すれば全国的に参考となる成果が期待されます。
最後に、地域連携・多機関連携の工夫です。例えばメロス言語学院の事例では自治体と連携して地域外国人向けの教育基盤整備を進めるとされています。地方自治体が外国人住民の日本語学習支援に直接関与する枠組みは、地域の課題に即した支援を可能にします。また名古屋の国際パートナーシップセンター等の事例では地域経済団体(商工会議所など)と日本語学校が連携し、企業への日本語教育提供モデルを普及するとしています。これは地域の企業ネットワークを活用して、企業側の協力を得ながら社員研修としての日本語教育を根付かせようとするアプローチです。さらに、佐賀・嬉野のモデルでは地元老舗旅館と東京の企業・コンサルティング会社が協働し、地域資源を活かした教育施設誘致を実現しています。
このように各事業はそれぞれの地域・業界のステークホルダーを巻き込み、官民連携や産学連携の体制を構築している点も特徴と言えるでしょう。
まず、ICTの活用が目立ちます。例えば、千駄ヶ谷外語学院の事例では「ビジネス日本語eラーニング教材と企業交流イベントを組み合わせた」就職支援を行うとされ、オンライン学習教材を積極的に取り入れています。また、全日本教育研究会・ミッドリーム日本語学校の事例では「AIを活用したビルメンテナンス業界向けの発話型学習教材の開発」に取り組む計画であり、人工知能を用いた対話練習教材という先進的手法が特徴です。さらに、岡山外語学院のプロジェクトでは、新たに創設される育成就労制度(技能実習制度に代わる新制度)を見据えて「オンライン日本語講習カリキュラムの開発」を行うとされ、遠隔で受講できる講習コンテンツの整備を進めています。このようにデジタル技術を取り入れることで、忙しい就労者でも学びやすくしたり、広域の学習者に対応したりする工夫が見られます。
次に、実践的・現場密着型の教育も多くの事業で重視されています。佐賀県嬉野市のモデルケースでは、旅館という現場で外国人留学生がアルバイト勤務をしながら日本語を学ぶ仕組みを構築し、教室の学びと職場経験を一体化させています。このようなインターンシップ組み込み型の教育プログラムによって、日本語学習が机上のものに留まらず、実際の業務・地域生活と結びつくように設計されています。同様に、石川のアリス学園による事業でもインド人技術者に対し就労前研修と就労後フォローアップを一貫して行うモデルを掲げており、職場定着を見据えた長期的な日本語教育支援が特徴です。また、TCJグローバルの事例では、外国人人材の企業紹介(就職あっせん)と日本語教育を一体化したサービス提供モデルを構築するとされています。これは人材紹介会社の機能と語学研修を組み合わせることで、「採用前の日本語研修→就労→就労後の継続研修」という切れ目ない支援を実現しようとするものです。
さらに、新しいカリキュラムや教材の開発も多くの事業でキーワードとなっています。JICEが中心となる事業では、宿泊・運送業界ごとに異なるニーズに対応する業種別日本語教育モデルカリキュラムの開発が掲げられています。これは業界団体と協力し、専門用語や接客表現など各業種に適した教材・カリキュラムを整える試みです。同様に、埼玉の与野学院日本語学校の事例ではプレA1レベル(超入門レベル)のカリキュラム開発がうたわれており、読み書きもままならない初心者向け教材の整備を進めています。これらの新カリキュラム策定は、他地域への汎用も視野に入れたモデルづくりと言え、完成すれば全国的に参考となる成果が期待されます。
最後に、地域連携・多機関連携の工夫です。例えばメロス言語学院の事例では自治体と連携して地域外国人向けの教育基盤整備を進めるとされています。地方自治体が外国人住民の日本語学習支援に直接関与する枠組みは、地域の課題に即した支援を可能にします。また名古屋の国際パートナーシップセンター等の事例では地域経済団体(商工会議所など)と日本語学校が連携し、企業への日本語教育提供モデルを普及するとしています。これは地域の企業ネットワークを活用して、企業側の協力を得ながら社員研修としての日本語教育を根付かせようとするアプローチです。さらに、佐賀・嬉野のモデルでは地元老舗旅館と東京の企業・コンサルティング会社が協働し、地域資源を活かした教育施設誘致を実現しています。
このように各事業はそれぞれの地域・業界のステークホルダーを巻き込み、官民連携や産学連携の体制を構築している点も特徴と言えるでしょう。
連携体制(他団体・企業・行政との協働構造)
上記のように実施内容にも表れている通り、全ての採択事業で何らかの協働体制が組まれており、日本語教育機関単独ではなく複数の組織がパートナーシップを構築しています。これは公募要件でもあり、応募に際して最低1つ以上の企業等連携先からの参加表明(かつ資金協力の意向)が必要とされました。そのため採択団体は、多くがコンソーシアム形式または主体と協力機関の明確な役割分担のもと事業を実施しています。
連携のパターンとしては、主に「日本語教育機関」+「企業」の組み合わせが核になっています。企業側は外国人材を受け入れる立場として、資金提供(研修費負担や寄付)や実習の場の提供、人材受入れ協力などを行います。一方、日本語教育機関(日本語学校や専門学校)はカリキュラム開発・教師派遣・研修実施など教育専門機能を担います。この基本形に加え、案件によっては自治体や経済団体、NPO等も加わる「三角連携・多角連携」となっています。例を挙げると、メロス言語学院の事業では自治体(地方公共団体)がパートナーとして参画し、行政と学校が協働で地域日本語教育基盤を整備します。国際パートナーシップセンター等の事業では、連携先に地元の経済団体が含まれ、産業界(地元企業の集合体)と教育機関が連携する構図です。JICEの事業では宿泊業・運送業の業界団体**(全国組織)が協力し、業界横断的なネットワークを背景にカリキュラム開発が進められます
。また、佐賀県嬉野市のケースでは、旅館企業・自治体支援・コンサル企業・学校運営企業という複数の主体がチームを組み、「地域創生×教育×雇用」の複合プロジェクトを構築しています。
各事業で連携体制の中核となる日本語教育機関は、文科省による日本語教育機関認定制度に関連して選ばれた認定日本語教育機関または認定予定の機関であり、質の担保された教育実施者です。全体統括機関であるデロイトトーマツコンサルティングの伴走支援の下、これら教育機関と連携各者が契約を交わし、実証事業を進めています。なお本事業では、連携先企業等から日本語教育機関への金銭的投資が採択要件とされており、例えば企業が研修費用を支払ったり、自治体が補助金を出したりする形で日本語教師の待遇改善や教材開発費に充当する仕組みが組み込まれています。このように、お互いのリソースを出し合いwin-winの関係を築くことが「好循環モデル」の肝であり、初年度採択団体はいずれも多様な連携構造でそのモデル構築に挑戦しています。
連携のパターンとしては、主に「日本語教育機関」+「企業」の組み合わせが核になっています。企業側は外国人材を受け入れる立場として、資金提供(研修費負担や寄付)や実習の場の提供、人材受入れ協力などを行います。一方、日本語教育機関(日本語学校や専門学校)はカリキュラム開発・教師派遣・研修実施など教育専門機能を担います。この基本形に加え、案件によっては自治体や経済団体、NPO等も加わる「三角連携・多角連携」となっています。例を挙げると、メロス言語学院の事業では自治体(地方公共団体)がパートナーとして参画し、行政と学校が協働で地域日本語教育基盤を整備します。国際パートナーシップセンター等の事業では、連携先に地元の経済団体が含まれ、産業界(地元企業の集合体)と教育機関が連携する構図です。JICEの事業では宿泊業・運送業の業界団体**(全国組織)が協力し、業界横断的なネットワークを背景にカリキュラム開発が進められます
。また、佐賀県嬉野市のケースでは、旅館企業・自治体支援・コンサル企業・学校運営企業という複数の主体がチームを組み、「地域創生×教育×雇用」の複合プロジェクトを構築しています。
各事業で連携体制の中核となる日本語教育機関は、文科省による日本語教育機関認定制度に関連して選ばれた認定日本語教育機関または認定予定の機関であり、質の担保された教育実施者です。全体統括機関であるデロイトトーマツコンサルティングの伴走支援の下、これら教育機関と連携各者が契約を交わし、実証事業を進めています。なお本事業では、連携先企業等から日本語教育機関への金銭的投資が採択要件とされており、例えば企業が研修費用を支払ったり、自治体が補助金を出したりする形で日本語教師の待遇改善や教材開発費に充当する仕組みが組み込まれています。このように、お互いのリソースを出し合いwin-winの関係を築くことが「好循環モデル」の肝であり、初年度採択団体はいずれも多様な連携構造でそのモデル構築に挑戦しています。
予算規模・事業規模の相違
各採択事業には、国から1団体あたりおおむね1,000万円程度の委託金(補助)が交付される予定です。初年度第1回では採択数が約13件となりましたが、当初計画では最大22件程度まで採択可能とされており、総事業規模は国費ベースで4億円規模となります。したがって、基本的にはどの採択団体も同程度(約1千万円規模)の予算で事業をスタートしていると考えられ、大きな予算格差はありません。もっとも、前述のように本事業では企業等からの追加投資や支援資金を呼び込むことが前提となっているため、実際の事業規模(総投入資金)や参加機関数は案件によって差異があります。
例えば、北海道東川町のモデルでは「企業版ふるさと納税」を活用して民間企業から寄附を募り、日本語教育・人材育成の基金としています。東川町では福祉人材育成プロジェクトの目標額を5億円という非常に大きな規模に設定しており、これだけの資金が集まれば事業継続・拡大が大いに図れることになります。一方、都市部の日本語学校による留学生就職支援などは、主に既存の留学生数十名規模を対象にした研修・イベント実施が中心で、参加学生数も例えば数十~百名未満程度と見込まれ、投入資金も国の補助+企業の研修委託費程度に留まるケースもあるでしょう。実際、佐賀・嬉野市の旅館内日本語学校では初年度の留学生受け入れが41名となっており、これをひとつのモデルケースとして拡張していく段階です。対照的に、JICEによる業界別カリキュラム開発は全国規模の業界団体を巻き込んだプロジェクトであり、開発した教材は当該業界で働く多数の外国人に波及しうるため、波及効果という点では大規模です。さらに、コンソーシアムを組む団体数にも差があります。単独の日本語学校と一企業の連携というシンプルな体制のものもあれば、複数の日本語学校や関係機関が一緒になった広域的なコンソーシアムも存在します(例:国際パートナーシップセンター+2校の連携体や、全日本教育研究会+ミッドリーム日本語学校+AI企業等の協働など)。
以上のように、予算・規模面では「国からの定額支援+民間資金」で概ね均一なスタートラインに立ちながら、民間からの追加投資額や参加団体数、対象外国人の人数の違いによって実質的な事業規模に幅がある状況です。モデル構築事業という性質上、今後成果が出た事例には追加資金投入や対象拡大がなされ、更なる発展を遂げる可能性があります。
例えば、北海道東川町のモデルでは「企業版ふるさと納税」を活用して民間企業から寄附を募り、日本語教育・人材育成の基金としています。東川町では福祉人材育成プロジェクトの目標額を5億円という非常に大きな規模に設定しており、これだけの資金が集まれば事業継続・拡大が大いに図れることになります。一方、都市部の日本語学校による留学生就職支援などは、主に既存の留学生数十名規模を対象にした研修・イベント実施が中心で、参加学生数も例えば数十~百名未満程度と見込まれ、投入資金も国の補助+企業の研修委託費程度に留まるケースもあるでしょう。実際、佐賀・嬉野市の旅館内日本語学校では初年度の留学生受け入れが41名となっており、これをひとつのモデルケースとして拡張していく段階です。対照的に、JICEによる業界別カリキュラム開発は全国規模の業界団体を巻き込んだプロジェクトであり、開発した教材は当該業界で働く多数の外国人に波及しうるため、波及効果という点では大規模です。さらに、コンソーシアムを組む団体数にも差があります。単独の日本語学校と一企業の連携というシンプルな体制のものもあれば、複数の日本語学校や関係機関が一緒になった広域的なコンソーシアムも存在します(例:国際パートナーシップセンター+2校の連携体や、全日本教育研究会+ミッドリーム日本語学校+AI企業等の協働など)。
以上のように、予算・規模面では「国からの定額支援+民間資金」で概ね均一なスタートラインに立ちながら、民間からの追加投資額や参加団体数、対象外国人の人数の違いによって実質的な事業規模に幅がある状況です。モデル構築事業という性質上、今後成果が出た事例には追加資金投入や対象拡大がなされ、更なる発展を遂げる可能性があります。
成功の兆し・モデル性がうかがえる事例
初年度の採択団体の中には、既に先行的な成果やモデルケースとして注目できる事例も生まれつつあります。その特徴的な例をいくつか挙げます。
・東川町(北海道)の外国人介護人材定着モデル
学校法人北工学園と東川町が連携したこのプロジェクトは、もともと町立日本語学校と旭川福祉専門学校(現・東川国際文化福祉専門学校)によって100名以上の外国人介護福祉士を育成・輩出してきた実績があります。その既存の取り組みに企業版ふるさと納税という新たな民間資金を組み合わせることで、地域ぐるみで外国人介護士を呼び込み定着させる好循環モデルを発展させようとしています。既に一定の成果を上げている地方創生の成功例に、更なる資金循環の仕組みを加えることで持続可能性を高める試みであり、他の過疎地域・介護人材不足地域にとってもモデル性の高い事例と言えます。
・温泉旅館内日本語学校による地域定着型モデル(佐賀県嬉野市)
株式会社アイ・シー・エイが運営する「ICA国際会話学院 嬉野校」は、日本で初めて旅館の敷地内に日本語学校を開設したケースとして注目されています。留学生たちは日中に日本語を学び、空き時間に旅館で働くことで現場経験を積み、卒業後にその地域で正社員就職・定住することを目指す“学び+働き”の直結モデルです。2025年4月の開校時点でインドやウズベキスタン等5カ国から41名もの留学生が集まり(平均年齢約26歳)スタートを切っており、早くも一定規模の人材育成が動き出しています。宿泊施設という地域資源の有効活用と、留学生に地方就労の機会を提供する仕組みを両立させた点が画期的で、他の観光地や人手不足業種への展開も期待されるモデルケースです。
・ICT/先端技術を活用した日本語教育モデル
東京のミッドリーム日本語学校等による取り組みでは、AI技術を活用した対話型教材の開発に乗り出しており、ビルメンテナンス業という特定産業の技能習得と日本語学習を融合させたコンテンツを作成中です。音声認識や対話エンジンによって現場で使える日本語表現を練習できる教材は、日本語教師の人手不足を補い学習者の自主学習を支えるツールとしてモデル性があります。完成すれば他業種向けへの横展開や、全国の技能実習・特定技能労働者への提供も可能であり、デジタル技術による日本語教育の高度化という点で成功が期待されます。
・外国ルーツ青少年のキャリア支援モデル
名古屋YWCAによる事業は、日本語学校と高等学院国際コースのノウハウを活かし、外国にルーツを持つ高校生や留学生の進学・就職を支える体制づくりを進めています。多文化背景の10代が日本社会で自己実現できるよう支援する取り組みはこれまで行政でも手薄な分野であり、本モデルが軌道に乗れば全国の外国人高校生支援の先駆けとなる可能性があります。既に名古屋YWCA高等学院では通信制高校サポートなどで実績を蓄積しており、それを地域企業や大学と結びつけてキャリア形成まで伴走する点にモデル性が見られます。
これらの事例はまだ事業開始から間もないものの、それぞれ「好循環モデル」の萌芽となりうる成果や仕組みを示しています。今後、各団体から進捗報告や成果データが公表されれば、例えば定着率の向上や日本語習得度合いの改善、企業からの追加投資誘発など成功の兆しを示す定量・定性データも明らかになってくるでしょう。初年度採択団体の中から、こうしたモデルケースが生まれ広がっていくことが、本事業全体の目的である「産業界等と日本語教育の好循環創出」に直結すると期待されています。
・東川町(北海道)の外国人介護人材定着モデル
学校法人北工学園と東川町が連携したこのプロジェクトは、もともと町立日本語学校と旭川福祉専門学校(現・東川国際文化福祉専門学校)によって100名以上の外国人介護福祉士を育成・輩出してきた実績があります。その既存の取り組みに企業版ふるさと納税という新たな民間資金を組み合わせることで、地域ぐるみで外国人介護士を呼び込み定着させる好循環モデルを発展させようとしています。既に一定の成果を上げている地方創生の成功例に、更なる資金循環の仕組みを加えることで持続可能性を高める試みであり、他の過疎地域・介護人材不足地域にとってもモデル性の高い事例と言えます。
・温泉旅館内日本語学校による地域定着型モデル(佐賀県嬉野市)
株式会社アイ・シー・エイが運営する「ICA国際会話学院 嬉野校」は、日本で初めて旅館の敷地内に日本語学校を開設したケースとして注目されています。留学生たちは日中に日本語を学び、空き時間に旅館で働くことで現場経験を積み、卒業後にその地域で正社員就職・定住することを目指す“学び+働き”の直結モデルです。2025年4月の開校時点でインドやウズベキスタン等5カ国から41名もの留学生が集まり(平均年齢約26歳)スタートを切っており、早くも一定規模の人材育成が動き出しています。宿泊施設という地域資源の有効活用と、留学生に地方就労の機会を提供する仕組みを両立させた点が画期的で、他の観光地や人手不足業種への展開も期待されるモデルケースです。
・ICT/先端技術を活用した日本語教育モデル
東京のミッドリーム日本語学校等による取り組みでは、AI技術を活用した対話型教材の開発に乗り出しており、ビルメンテナンス業という特定産業の技能習得と日本語学習を融合させたコンテンツを作成中です。音声認識や対話エンジンによって現場で使える日本語表現を練習できる教材は、日本語教師の人手不足を補い学習者の自主学習を支えるツールとしてモデル性があります。完成すれば他業種向けへの横展開や、全国の技能実習・特定技能労働者への提供も可能であり、デジタル技術による日本語教育の高度化という点で成功が期待されます。
・外国ルーツ青少年のキャリア支援モデル
名古屋YWCAによる事業は、日本語学校と高等学院国際コースのノウハウを活かし、外国にルーツを持つ高校生や留学生の進学・就職を支える体制づくりを進めています。多文化背景の10代が日本社会で自己実現できるよう支援する取り組みはこれまで行政でも手薄な分野であり、本モデルが軌道に乗れば全国の外国人高校生支援の先駆けとなる可能性があります。既に名古屋YWCA高等学院では通信制高校サポートなどで実績を蓄積しており、それを地域企業や大学と結びつけてキャリア形成まで伴走する点にモデル性が見られます。
これらの事例はまだ事業開始から間もないものの、それぞれ「好循環モデル」の萌芽となりうる成果や仕組みを示しています。今後、各団体から進捗報告や成果データが公表されれば、例えば定着率の向上や日本語習得度合いの改善、企業からの追加投資誘発など成功の兆しを示す定量・定性データも明らかになってくるでしょう。初年度採択団体の中から、こうしたモデルケースが生まれ広がっていくことが、本事業全体の目的である「産業界等と日本語教育の好循環創出」に直結すると期待されています。
おわりに
以上、文部科学省「好循環モデル構築実施団体」初年度第1回公募の採択結果について、団体の種類、地域分布、対象外国人層、実施内容、連携体制、規模感、そして注目事例に至るまで、多角的に分析しました。全体を通じて感じられるのは、日本語教育を通じた外国人材受入れ支援において、官民の創意工夫あるモデル事業が全国各地で動き出したという動向です。これらのモデルが今後軌道に乗り、好事例として定着・発展していけば、我が国の日本語教育と共生社会づくりにおける貴重な財産となるでしょう。そのためにも、引き続き各事業の成果を検証し、効果が高かった取組は水平展開しつつ、課題が見えた点は改善していくPDCAが重要です。本記事が、今後の日本語教育施策と地域連携モデルの発展に寄与する一助となれば幸いです。
新着の記事
- 【大久保】エリートビジョン日本語学校採用説明会
- 【オンライン日本語学校】Akira Online Japanese School TOKYO 採用説明会
- 【大会要約】令和7年度 文部科学省日本語教育大会― 認定日本語教育機関の申請を考える学校が知っておくべきこと ―
- 【千葉県千葉市】関東外語学院 採用説明会
- 第16回埼玉地区日本語教育機関合同採用説明会開催のお知らせ
- 【東京都北区】学校法人JET日本語学校採用説明会
- 【千葉県我孫子市】AJS国際学園 採用説明会
- 【東京都世田谷区】東京ひのき外語学院 採用説明会
- 【福岡市中央区】Meiji Academy 採用説明会
- 【重要】年末年始の問い合わせについて