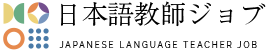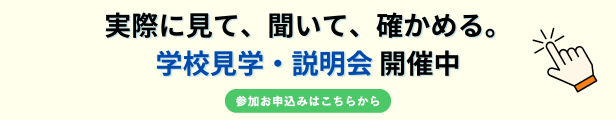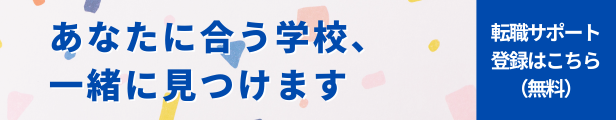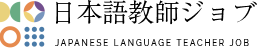国家資格ができても、日本語教師の給料は上がらない本当の理由
「国家資格になれば、日本語教師の給料も上がりますよね」
「制度が整えば、待遇も改善されるんですよね」
こうした声を耳にすることはとても多いです。期待する気持ちはよく分かります。資格や制度が整えば、業界全体が底上げされるのではないか――そう願うのは自然なことです。
けれども実際には、思ったほど単純な話ではありません。夢を壊すためではなく、むしろ現実を知ることで、自分のキャリアをよりよく考える助けにしてほしいと思い、このテーマについて少しお話しします。
「制度が整えば、待遇も改善されるんですよね」
こうした声を耳にすることはとても多いです。期待する気持ちはよく分かります。資格や制度が整えば、業界全体が底上げされるのではないか――そう願うのは自然なことです。
けれども実際には、思ったほど単純な話ではありません。夢を壊すためではなく、むしろ現実を知ることで、自分のキャリアをよりよく考える助けにしてほしいと思い、このテーマについて少しお話しします。
未経験者が短期で入れ替わってしまう現実
日本語学校は労働集約型の典型です。人件費の割合が大きく、給与を大幅に上げるのは容易ではありません。その結果、未経験で入ってきた先生が定着せず、数年で辞めてしまうケースが後を絶ちません。
これは必ずしも学校が「使い捨てにしよう」と考えているからではありません。むしろ長く勤めてもらいたいと願う学校も多いでしょう。それでも、授業準備や学生対応に追われる過酷な労働環境の中で、待遇がなかなか改善されず、自然に淘汰が起きてしまうのです。
一方で、明らかに「新陳代謝を前提にしている」と思われる学校も存在します。若手や未経験の先生を低賃金で採用し、数年働いたら入れ替えることを織り込み済みにしているような運営です。経営側から見れば収益構造を守る合理的な判断なのかもしれませんが、働く側からすれば「育ててもらう場」ではなく「消耗する場」となってしまいます。
理想は、未経験者をじっくり育てて専任として長く働ける環境を作ることです。しかし構造的にそれが難しく、結果として「短期で人が入れ替わる」サイクルが業界全体に根づいてしまっているのが現実です。
これは必ずしも学校が「使い捨てにしよう」と考えているからではありません。むしろ長く勤めてもらいたいと願う学校も多いでしょう。それでも、授業準備や学生対応に追われる過酷な労働環境の中で、待遇がなかなか改善されず、自然に淘汰が起きてしまうのです。
一方で、明らかに「新陳代謝を前提にしている」と思われる学校も存在します。若手や未経験の先生を低賃金で採用し、数年働いたら入れ替えることを織り込み済みにしているような運営です。経営側から見れば収益構造を守る合理的な判断なのかもしれませんが、働く側からすれば「育ててもらう場」ではなく「消耗する場」となってしまいます。
理想は、未経験者をじっくり育てて専任として長く働ける環境を作ることです。しかし構造的にそれが難しく、結果として「短期で人が入れ替わる」サイクルが業界全体に根づいてしまっているのが現実です。
給料が上がらないのは、経営者が冷たいからではない
データは日本語教師の給料調査2025年版 東京・都市圏・地方でどう違う?より
「給料を上げたい」という経営者は少なくありません。それでも現実には、授業料を上げることが難しい中で人件費を増やせば、すぐに赤字になってしまいます。日本語学校は他の産業以上に不安定なリスクを抱えています。直近ではコロナによる学生の激減がありましたし、在留資格(COE)の交付率が極端に下がることもあります。加えて、政治的な不安定さや天災などで、学生が激減することも珍しくありません。
そうした時期を乗り越えるためには、利益をすぐに給与に回すのではなく、ある程度は「学校の貯金」として蓄えておく必要があります。結果として「上げたいけど上げられない」という状態が続き、先生は定着しにくくなり、業界全体で慢性的な人材不足につながっています。
これは経営者の冷たさの問題ではなく、労働集約型という産業構造が抱えるジレンマそのものです。たとえば介護や保育の分野では国家資格が整備されていますが、それでも低賃金が長年の課題になっています。飲食業界でも同じく、人件費を抑えなければ事業が回らず、離職と人材不足が常態化しています。
つまり日本語教育だけの特殊な問題ではなく、「人の労働力そのものが価値を生む産業」全般に共通する構造的な限界だということなのです。
「給料を上げたい」という経営者は少なくありません。それでも現実には、授業料を上げることが難しい中で人件費を増やせば、すぐに赤字になってしまいます。日本語学校は他の産業以上に不安定なリスクを抱えています。直近ではコロナによる学生の激減がありましたし、在留資格(COE)の交付率が極端に下がることもあります。加えて、政治的な不安定さや天災などで、学生が激減することも珍しくありません。
そうした時期を乗り越えるためには、利益をすぐに給与に回すのではなく、ある程度は「学校の貯金」として蓄えておく必要があります。結果として「上げたいけど上げられない」という状態が続き、先生は定着しにくくなり、業界全体で慢性的な人材不足につながっています。
これは経営者の冷たさの問題ではなく、労働集約型という産業構造が抱えるジレンマそのものです。たとえば介護や保育の分野では国家資格が整備されていますが、それでも低賃金が長年の課題になっています。飲食業界でも同じく、人件費を抑えなければ事業が回らず、離職と人材不足が常態化しています。
つまり日本語教育だけの特殊な問題ではなく、「人の労働力そのものが価値を生む産業」全般に共通する構造的な限界だということなのです。
学費を上げずに「質」だけ求めるのは無理がある
労働集約型の日本語学校では、そもそも収益性が高くありません。先生の人数を増やさないと学生を受け入れられず、一人の生産性を大きく伸ばすことも難しいからです。そうした中で待遇を改善するための第一歩は、どうしても「学費を適正に上げること」になります。収益に余力がなければ、どれだけ制度を整えても給与改善に回せる資源は生まれません。
ここで忘れてはいけないのは、学費を据え置いたまま「教育の質」だけを高めようとすることは根本的に無理があるということです。どんなに制度を整えても、収益に余力がなければ先生の待遇改善に回せる資源は生まれません。
ところが国は、認定制度を通じて学校に「質の向上」ばかりを求めています。肝心の学費改定や財政的な支援についてはほとんど触れず、「やれ」とだけ言っているのが現状です。これは言い換えれば、ガソリンを入れずに車を走らせろと命じているようなものです。
質を求めるなら、学費を上げやすい制度的な後押しや、財政的な補助を同時に進めるべきです。それをせずに現場にばかり負担を押しつけるやり方は、現場を知らない机上の理屈に過ぎず、教師たちから見れば不誠実と映るでしょう。
ここで忘れてはいけないのは、学費を据え置いたまま「教育の質」だけを高めようとすることは根本的に無理があるということです。どんなに制度を整えても、収益に余力がなければ先生の待遇改善に回せる資源は生まれません。
ところが国は、認定制度を通じて学校に「質の向上」ばかりを求めています。肝心の学費改定や財政的な支援についてはほとんど触れず、「やれ」とだけ言っているのが現状です。これは言い換えれば、ガソリンを入れずに車を走らせろと命じているようなものです。
質を求めるなら、学費を上げやすい制度的な後押しや、財政的な補助を同時に進めるべきです。それをせずに現場にばかり負担を押しつけるやり方は、現場を知らない机上の理屈に過ぎず、教師たちから見れば不誠実と映るでしょう。
本当の意味で変わるために
日本語教育が持続可能な産業になるためには、学校が「人材に投資すること」をコストではなく価値の源泉として捉えることが必要です。特色ある教育やブランド力を持ち、学費を上げても学生に選ばれる学校づくりができれば、ようやく給与改善に回せる余地が生まれます。
そして制度を作る側にも責任があります。教育の質だけを求めるのではなく、学費を適正化できる環境や財政的な支援をセットで整えてこそ、初めて待遇改善につながるのです。
そして制度を作る側にも責任があります。教育の質だけを求めるのではなく、学費を適正化できる環境や財政的な支援をセットで整えてこそ、初めて待遇改善につながるのです。
おわりに
国家資格や制度の整備は、大切な前進です。しかし、それが魔法の杖のように給与を引き上げてくれるわけではありません。むしろ制度が形だけ先行し、現場に負担ばかりを押しつければ、教師は疲弊し、人材不足はさらに深刻化するでしょう。
だからこそ私たちは、制度に過度に期待するのではなく、その仕組みが持つ限界を理解したうえで、自分のキャリアをどう築いていくかを主体的に考える必要があります。
変化を起こすのは、学校の経営判断と先生一人ひとりの歩み、そして制度を設計する側の本気度です。この三つがそろって初めて、日本語教師の未来は少しずつ明るくなっていくのではないでしょうか。
だからこそ私たちは、制度に過度に期待するのではなく、その仕組みが持つ限界を理解したうえで、自分のキャリアをどう築いていくかを主体的に考える必要があります。
変化を起こすのは、学校の経営判断と先生一人ひとりの歩み、そして制度を設計する側の本気度です。この三つがそろって初めて、日本語教師の未来は少しずつ明るくなっていくのではないでしょうか。
新着の記事
- 【大久保】エリートビジョン日本語学校採用説明会
- 【オンライン日本語学校】Akira Online Japanese School TOKYO 採用説明会
- 【大会要約】令和7年度 文部科学省日本語教育大会― 認定日本語教育機関の申請を考える学校が知っておくべきこと ―
- 【千葉県千葉市】関東外語学院 採用説明会
- 第16回埼玉地区日本語教育機関合同採用説明会開催のお知らせ
- 【東京都北区】学校法人JET日本語学校採用説明会
- 【千葉県我孫子市】AJS国際学園 採用説明会
- 【東京都世田谷区】東京ひのき外語学院 採用説明会
- 【福岡市中央区】Meiji Academy 採用説明会
- 【重要】年末年始の問い合わせについて